カメラ?ソフトの機能?3DCGモデラーに必要な知識とは?
(更新日: 2021/12/11)

実際、学校では、デッサンをしたり、illustratorやPhotoshopなども使ってみたりはしますが、実際モデリングする際こういった事に注意して、こういったことを考えながら…という詳しい事は教わることが少ないかと思います。
なので、どういった知識が必要か…その理由は何故か…ということを自分が実際プロとして3DCGモデラーをやってみて、思った事、必要と感じた事を説明していきます。
筆者オススメ!)Mayaを全く触ったことない人向けの動画講座(Udemy)
現役クリエイターが教える、現場で使われている3Dモデリングの基礎を学習となっている。
( こんなことが分かります)
✔ モデリングするのに必要な知識
3DCGモデラーにオススメな本)
モデリングする際に必要な知識
自分がモデリング作業を実際の現場でしてみて、これは必要だなということを書いていきます。
実際自分は、専門学校の時に先生に教えてもらった事以外に様々な事を学んだので、少しでも参考になればと思います。

カメラ、パースの知識
カメラの広角、望遠、魚眼レンズといった知識です。
カメラの構造の理解した方が、より理解が進むでしょう。
1点透視図法、2点透視図法、3点透視図法といったパースの知識も念のためつけていくといいでしょう。
望遠レンズって??
「画角の狭いレンズ」・「焦点距離が長いレンズ」ということになる。望遠鏡のように遠くを写すために、また近距離にある被写体を大きく写すために使われる。
3DCGのmayaでは、実際の望遠レンズと違い、望遠にすればするほど、奥行きが詰まって見えるようになります。
広角レンズって??
標準レンズよりも「画角の広いレンズ」・「焦点距離が短いレンズ」ということになり、簡単に言うと望遠の対義語のようなイメージとなっています。
画角が狭い望遠レンズとは逆に広角は画角が広いので、風景をより広く見せることができますが、広角にすればするほど、樽状に歪んでしまうという欠点もあります。
3DCGのmayaでは、奥行きが実際のレンズよりも出来てしまい、より不自然になってしまう傾向があります。
理由
ソフトのカメラのデフォルトの設定だとかなりの広角ぎみでそのまま作ると、歪んだ状態で作ることになる。
他にもアニメ作成をしていた時、BG単体のカットをたまに任される…といったこともあったので、カメラの知識がないと、このカットが広角気味なのか望遠気味なのかという判断もわかりません。
モデリング作業する際は望遠に設定すること。
例)mayaだとデフォルト45なので、80~90の望遠にすること。
それに、このカット俯瞰、煽り気味で使う事があるから…など専門用語で指示されます。
使われた時、え?それ、どういう意味ですか??なんて聞いてたら、評価はガタ落ちになってしまいます。(基礎中の基礎なので…)
こういった知識もいわば、カメラの知識と同じなのでしっかりと身に着けておくべきです。
とのことで、モデラーでもカメラの知識は必須と言えましょう。
俯瞰って??
一言で言ってしまうと、高いところから見下ろす事です。
言葉でいうよりも、絵で見た方が分かりがよりいいと思いますので…下に参考サイトを載せておきます。
あおりって??
下から対象を見上げる構図のことを言います。
俯瞰と逆の構図ですね。
煽り、俯瞰の参考サイト)
マンガの基本構図5パターンと描き方のコツを参考実例を交えて解説! | テラストーリーズ
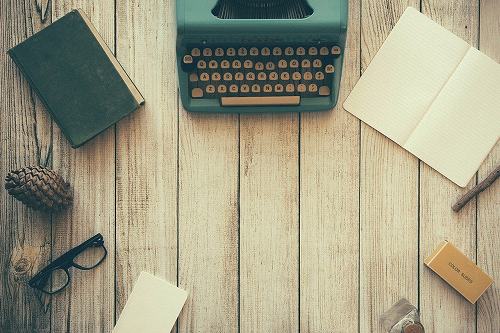
物、人の構造をしっかり理解すること。
例えば、マウスを作るとしましょう。あのネズミの方ではなく、クリックしたりするマウスです。
では、ただいくつかの写真を見ながら作ることもできますが、それでは後々構造が複雑なもので祖語が出てしまい、つまずいてしまいます。
じゃあ、どういった事を気にして作るべきか…
それは、上のマウスの例えに乗っ取って、説明します。
マウスというのは、人が握って使うものですよね?
人差し指でクリックして親指と主に薬指、補助として小指も使ったりします。
ということは、手の構造を理解していないといけないのです。
どういった形が手で握りやすいのか、握りやすいのかといったことです。
自分も新人教育で新人に教えていた時期に実際にあった新人のミスなのですが、クリックするところを左クリックと右クリックの隙間を作らずにやっていたのです。
条件次第でそこまで作らなくていいという場合がありますが、この時はできるだけリアルにという条件下では、隙間をしっかり作るべきですね。
でなければ、クリックできないですから笑
そういったことで、構造を理解していなければ、よりリアルに作れないし、構造が複雑な物だとそういった知識や意識がないと躓いてしまいます。
それでは、どうやって構造を学んでいけばいいか。
それは、本を使ったり、最近ではYouTubeなどの動画でも勉強できます。
本を使う場合は、人体の構造やモデリングの仕方の本 が主に使いますね。
3DCGソフト、Adobe Photoshopとillustratorの機能の把握
3DCGソフトの機能は、当たり前ですよね。
3DCGソフトをメインで使用するのですから。
photoshopとillustratorの知識は?となると上のモデラーとは??の項目でも説明した通り、テクスチャ作成する際に作ったりします。
一応、メルスクリプト(プログラミングの知識も多少)も多少必要になります。
なくても…大丈夫ですが、あれば他の人よりも差がつけることができます。
となみに…何故プログラム(メルスクリプト)が必要かというのは、モデリング機能の項目だけでは、効率よく作成できない場合があります。
そういった場合、自分で効率のいい機能を作成するということができます。
もしくは、有料、無料のプログラムがあったりするので、それをダウンロードして使ったりするのもありでしょう。
melスクリプトって??
MEL は UNIX のシェル スクリプトの流れを受け継いでいます。すなわち、MEL は他の言語のようにデータ構造の操作や関数のコールを行ったり、オブジェクト指向の手法を利用するのではなく、実行コマンドに基づいて目的を達成しているようです(UNIX シェルの実行コマンドと同様です)。
例えば、オブジェクトを生成した場合やオブジェクトを押し出しを行った場合など殆どの行動のプログラムがメルスクリプトエディタに表示されます。
なので、こういった行動をする場合、どういったプログラムがされているか他に比べてすぐわかりやすいというメリットがあります。
自分は、それを参考にして、書き換えて使っていたりしました。
参考記事)mayaのヘルプ、melの概要
メインでテクスチャ作成を作る際に使用します。
なので、photoshopの使い方、機能をしっかり把握しておくべきでしょう。
これは、photoshopで作りずらいテクスチャ、例えば、看板などのテクスチャを作成したりするのは、こちらのillustratorの方が作りやすいでしょう。
これもphotoshopと同じで使い方や機能をしっかり把握しておくべきでしょう。
参考記事)Adobeこ公式サイトからillustratorとは??
キャラクターのモデリングは、結構難しい!
動かす前提で作られるキャラクターのモデリングは、初心者が作るにはかなり難しいです。
他のモデリング作業に比べ、考えることが多いからなんですが、下記に理由を書きました。
理由
人の構造を考えながら作らないとならない。
これは、動かす前提でなくても考えないといけないですね。
人の構造はかなり複雑でどういった風に動くかどこまで動くかなどなど考えながら作らないといけないので、最初に作るにはハードルが高いです。
動かす際のポリゴンの割り方を考えるという項目が増える
これは、実際リギング、モーションをつける経験がないと分からなかったり、リテイクがきたりする部分がある。
特に関節部分のポリゴンの割り方です。
ローポリなのかハイポリ気味なのかによってどれくらいポリゴン数を割るのかが決り、どのくらい割れば、自然に関節を動かせるのかというのは、動かした経験がないと判断がつきませよね。
実際に自分も作ってみて、いざボーン入れてスキニング作業しつつ動かしてみるとうまくいかなかった経験があります。
それは、スキング作業が悪い、ボーンの位置が悪いのではなく、関節部分のポリゴンの割が足りないといった事態に陥ったんです。
実は、このスキング作業でポリゴンの割が足りないことに気づき、修正するというのはかなり手間で大きな時間のロスになります。
その理由として、まずボーンを外し、ヒストリを削除した後、割を入れる。
そうすると、UV情報もごちゃごちゃになるので再度UV展開…とかなり前の作業まで戻されてしまいます。
こういったロスを防ぐには、ひたすら経験を積むしかありません。
ですが、経験を積む段階で失敗ばかりして仕事でヘマをやらかすわけにもいかないと思うので、動画などを見て、どういった割り方をしているのかを確認してやってみるのが良いでしょう。
※できれば、十分練習をしてから望むのがベストなんですがね笑
人体のモデリングのモデリング方法がイマイチ分からないという方にオススメな本はこちら▶絶対損しない!3DCGモデラーに必要な3つの本 - 菊飛movie
他の小物よりシビアにポリゴン数を制限される状況下に置かれる
ローポリなのか…ハイポリなのかでどのくらいポリゴンをさくのか、どの部分はテクスチャで表現するのかを判断しないといけません。
それは、今までのモデリング知識と情報、経験がないとできません。
そもそもどんな感じで1体作るとどのくらいのポリゴン数になるのかが判断できませんよね。
それに、ローポリで作成するのかハイポリで作成するのかで作り方、特にポリゴンの割り方を考えて作成しないとならないので、大きく違ってきてしまいます。
ローポリゴン、ハイポリって??
ローポリ(ポリゴン数が少ない)、ハイポリ(ポリゴン数が多い)というもので、ローポリは、基本三角ポリゴンで作成し、ポリゴンを削減します。
逆に、ハイポリは形を四角ポリゴンで作成し、ポリゴン数を使います。
ポリゴン数が多いので、ローポリよりハイポリの方がリアルな形を作成できます。
最後に…
カメラの知識や物の構造は、調べて身につけられますが、ソフトの機能やモデリングの経験といった事は、ひたすら作りまくってやるしかありません。
その際、時間をじっくりかけるのも重要ですが、早く正確に作るということもプロでは求められます。
今のうちからそういう頭で作成しておくと、いざプロの現場に!となった時あたふたせずに冷静に対処できるでしょう。
